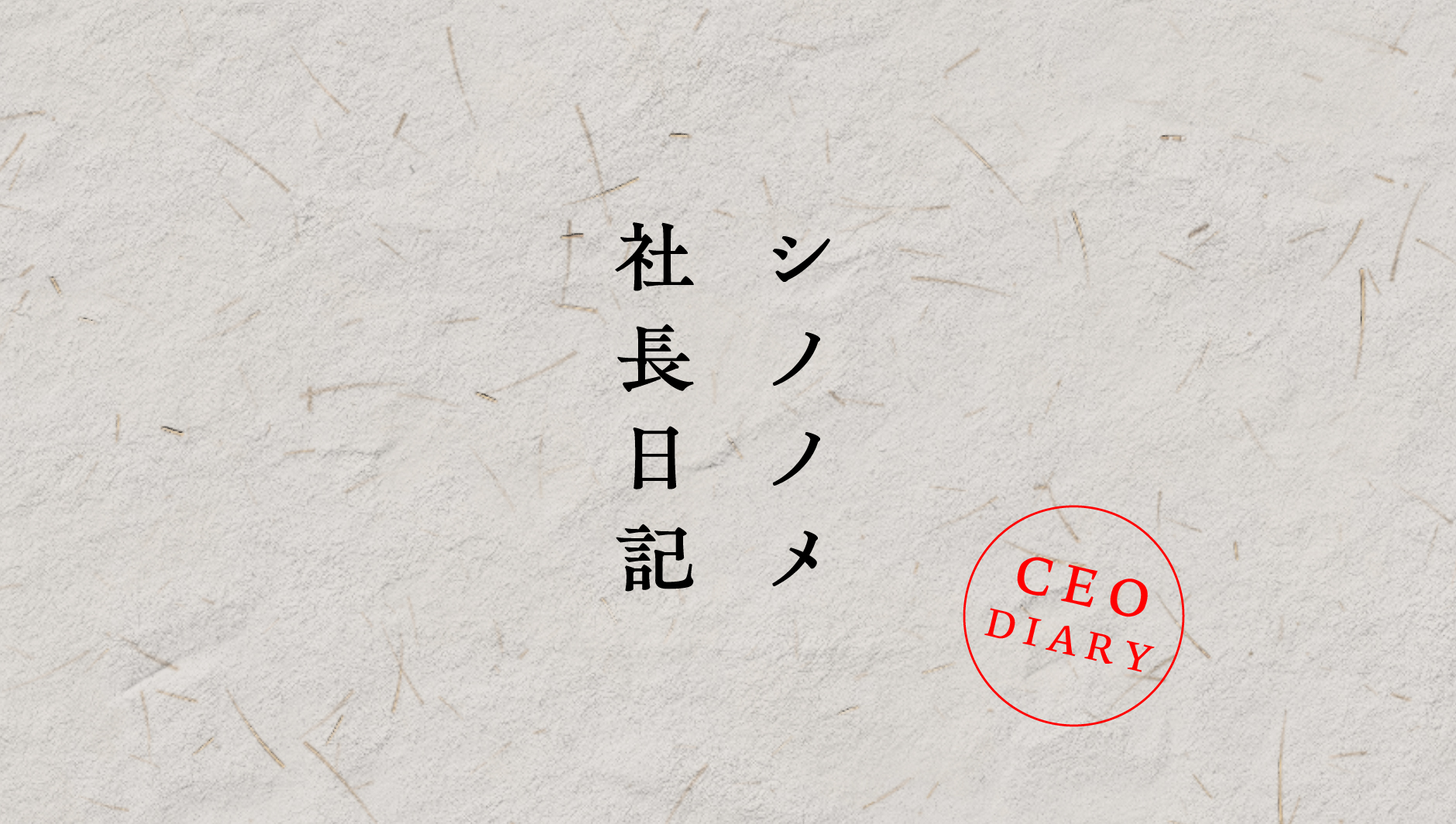
事業を始めて来週で3期目、少し休暇を頂いたのでこれまでの約2年間を振り返ろうと思います。
HR(人事・採用)コンサルテーションという、狭い領域の中で果たして事業が成り立つのか?という思いを抱えながらどうにか前に進めて約2年、直近の仕事では財務・法務・ビジネスの各分野と並び人事採用のアドバイザーとして企業のデューデリジェンスに参加する機会を頂き、深く感謝するとともに一定の世の中からのニーズを肌で感じています。
HR(人事・採用)はとてもファジー(曖昧)な領域です。
採用一つ取っても長期にわたり活躍する輝かしい人材もいれば、採用・育成のコストに対しマイナスのまま諸々の事情で職を離れる人もいます。それどころか入社によって企業とその周りの人に悪影響を与える人すらいます。
何度か書いていることですが、これらは全て採用数“1”なのが事態を複雑化します。スプレッドシート上に無機質に並んだこれらの“1”を掻き集め、単純にデータ・ドリブンな意思決定をすることは大きなミスリードにすらなり得ます。
集客や財務と比較するとこのバラつきはとても大きく、現在主流のキャッシュフローに重きを置いた経営スタイルとは時に相性がとても悪くなり得ます。
事実、僕たちの仕事は財務のプロフェッショナルから観ると説得力に欠けるように見え、よく衝突をしてきました。(そして大概の場合煮え湯を飲まされることになります)
この約2年、何かを残せたか?という問いに対していくつか成果を上げることはもちろんできます。人によっては、“採用の効率化によってEBITDAにポジティブ影響を与えた”と評価をしてくれるかもしれないし、採用総数の増加がドライバーになってスケールメリットを獲得することができたと理解していただけるかもしれません。当初はこれらの評価を僕らは手放しに喜びました。
しかしながら、これらは全てスプレッドシート上から見える風景で、血が通っていません。これはとても良くない。
僕は“自分の個性を炸裂させる場所で働ける人の割合が、その国の幸せ度と相関する”と割と本気で考えており、この目的に対しては全く近づけていない。そうした点でまだあらゆる面で道半ばと考えています。
しかしながらHR(人事・採用)というとてもあやふやな領域で業を営む上で自分たちが大切にして生きていきたい姿勢はおぼろげに見えてきた気がします。少なくとも今の僕らにおける現時点でのベストな見解は、
“デジタルに理解し、アナクロに向き合う”
あやふやさと隣り合わせのHR(人事・採用)であっても、デジタルに理解を進めなければ、現在の効率化・高機能化された経営のスピードについて行くことはできない。そしていつしか同じテーブルにすら乗ることができず、HRはその可能性を失い、固定費を構成する1アイテムと化してしまいます。
但し、それだけでは足りません。デジタルのみでHRの課題と向き合うのは時に弊害にすらなり得ます。スプレッドシート内のHRに関連する箇所に刻まれるのは一人ひとりの人生の選択の結果であって、それはデジタルな分析だけでは向き合えない。むしろおこがましい。アナクロに数値の変化と向き合い、血を通わせる必要があります。
前職を辞して2年強、当初描いていた目的地と目指すところは変わらねど、道程の険しさに、時に嫌気がさしながらも気を吐き続けてきたきがします。そしてこれを続けて行くつもりです。





